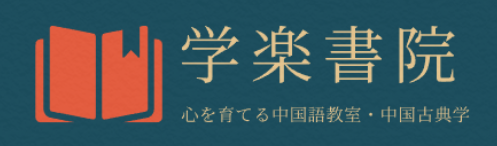遅ればせながら新年おめでとうございます。本年も学楽書院をよろしくお願いします。あっという間に1月も後半に入りますね。気がつくと「大寒」も過ぎました。もうしばらくすると「立春」です。季節はどんどん動いていますね。
「春捂秋冻」 chūn wǔ qiū dòng 春は厚着して秋は薄着する
中国のことわざにこのようなものがあります。春は季節がどんどん陽気を増してきますが、まだ風は冷たく邪気を避けるためにも適度に厚着が必要です。また秋は冬の寒さになれるためにも少し薄めにすごす、といった意味です。
では今回は2月の時期の養生法をご紹介します。
気候の特徴
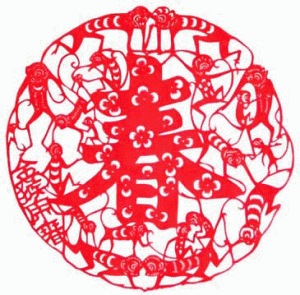
2月は春の始まりです。「立春」「雨水」の二節気を含みます。「立春」は二十四節気の始まりで、春はこの日から始まります。「立春」を過ぎると、万物はよみがえり、大地は生気にあふれ、木々は芽生えはじめます。
一年の四季はここから始まるのです。「雨水」の節気は冬が去り春が訪れ、湿度がだんだん上昇し、冷たい空気は依然活動が頻繁です。朝晩はやはり寒いです。「雨水」の節気は雨が多く、空気が湿潤になり、天気は暖かいけれど乾いた暑さではなく、万物の成長にいっそう適しています。
中医学的考えでは、春は木・肝に属します。(陰陽五行の考え方で万物を木、火、土、金、水に分類する考え方。)
春は養生の中心は肝を守ることで、肝を守るには心から取りかかり、気持ちをのびのびとさせ、怒りっぽくならないようにします。
養生のポイント

春は冷たい空気が活発な時期ですので適当に厚着することです。二月は日中が長くなってきて、日差しが暖かく、気温も上昇してきて、日照、降水もだんだんと多くなってきます。
民間のことわざで「立春の雨がやってくると早起き遅寝する」というのがあります。人々は秋冬の養生を経て、春が来ると労働を始めるのです。春の養生は春の陽気のはじまり、万物の始まりの特徴に合わせて、だんだんと秋の養生から春の養生へと移行して陽気を守ることに注意します。立春以降、気候は乾燥していきますので水分も十分に補いましょう。
春の飲食の養生
春は陽気の始まりです。辛い物、甘い物を摂取し、すっぱいものはさけましょう。酸味は肝に入り、収斂性を帯びるので、陽気の発生と肝気(中医学で消化不良などの症状)の解消には役立たないので、食養生は内臓に合わせるのがよいでしょう。
食べて良いもの
辛くて温めるもの(なつめ、トウチ、ねぎ、香菜、ピーナッツ、ニラ、エビなど)
良くないもの
刺激の強いもの
オススメレシピ『クコと山芋のおかゆ』
材料
クコ20g 山芋30g もち米50g
作り方

クコと山芋、もち米を鍋に入れ適量の水を加え、強火で煮たのち弱火に変えてゆっくりと半時間ほどお米が柔らかくなるまで煮る。温かいうちにいただく。
効果
クコは腎によく肝にやさしい食べ物で、山芋は脾を強くし腎によく、もち米は胃と合う。ともに肝に優しく、腎によく脾を健やかにする。